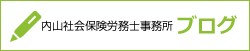労働保険・社会保険手続代行
正確な処理をスピーディーに!
従業員の入退時をはじめ、各種事務処理の手続きを代行します。
労働保険・社会保険の手続きにはポイントがあります
労働保険や社会保険の手続きは面倒なことも多く、自社で行うと時間やコストがかかります。
各種届書には、ちょっとしたポイントがあり、そこが未記入であったり記入方法が違うと、役所ですぐに処理をしてもらえないことや、認められないことがあります。
当事務所では、早く正確な手続きはもとより、そのポイントを確実に整理し書類作成を行います。
こんなお悩みはありませんか?
- 役所に聞けば分かることではなく、会社側の立場でアドバイスが欲しい。
-
社会保険に未加入の従業員がいる(特にパート・アルバイト)
-
年金事務所からの調査が入り対応に困っている
-
毎月の社会保険料に苦しんでいる
- 面倒な手続きは、アウトソーシングして本業に専念したい。
- 役員(非常勤役員)の社会保険・労災保険はどうすればよいのか?
- パート、アルバイトの社会保険、労働保険はどうすればよいのか?
- 従業員の仕事中や仕事以外のケガや病気で、どのような保障が受けられるのか分からない。
どんな雇用形態だと労働保険・社会保険に加入しないといけないの?
社会保険は法人事業所であれば事業主も含め、全ての従業員(パート・アルバイトも含む)が加入しなければなりません。また、雇用保険は適用事業所に雇用される従業員(パート・アルバイトも含む)は、原則として加入しなければなりません。ただし、以下の場合は適用除外となります。
例外的に被保険者とならない従業員
☑ 労災保険
- 原則として同居の親族を除く全ての従業員
☑ 雇用保険
- 65歳に達した日以後、新たに採用される従業員
- 1週間の所定労働時間が20時間未満の従業員
- 継続して雇用される期間が31日未満の従業員
☑ 厚生年金保険
- 70歳以上の従業員
- 2ヶ月以内の期間を定めて雇用する従業員
- 通常の従業員の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3未満の従業員
☑ 健康保険
- 75歳以上の従業員
- 2ヶ月以内の期間を定めて雇用する従業員
- 通常の従業員の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3未満の従業員
「労働保険 年度更新」「社会保険 算定基礎届」について
労働保険 年度更新とは
労働保険(労災保険と雇用保険)の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位として計算します。すでに納付した前年度の保険料を清算するために確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料の申告・納付を同時に行うことを年度更新といいます。
この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
【対象となる労働者】
労働保険・・・労働者全員が対象となります。従って外国人やアルバイト・パートも対象です。
雇用保険・・・被保険者が対象です。(被保険者とは、31日以上引き続いて雇用される見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間以上であれば被保険者になります。)
社会保険 算定基礎届とは
社会保険(健康保険と厚生年金)の保険料・保険給付・各年金の算定にあたっては、標準報酬月額に基づいて決定されます。このため、被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が出ないように、毎年1回 標準報酬月額を見直し、決定します。
決定された標準報酬月額は、基本的に9月から翌年8月までの1年間使用しますが、この間に固定的賃金の増減があった場合、随時変更することもあります。
算定基礎届の手続きは、毎年7月1日から7月10日までの間におこなわなければなりません。
【対象となる従業員】
届出の対象となるのは、7月1日 現在の全被保険者です。ただし、6月1日以降に被保険者となった従業員は、その年では届出の必要はありません。
被保険者とは・・・労働時間と労働日数がそれぞれ一般社員の4分の3以上であるとき被保険者となります。
「社会保険の未加入事業所」と「パート・アルバイトの社会保険未加入」
~なぜ、あなたの会社が「社会保険未加入」だと分かり適用対象事業所になったのか~
社会保険未加入における会社のリスク
健康保険・厚生年金保険などの社会保険は、会社や従業員の事情に関係なく、法人の会社であれば加入が義務付けられており、未加入や脱退は認められていません。もし、加入義務を怠っていた場合、会社にどのようなリスクがあるのでしょうか。
近年、少子高齢化が進展し、雇用環境の変化や貧困・格差の問題など、社会が大きく変化していく中、社会保障制度の改革とともに、負担を先送りにしないために財政健全化を同時に達成する「社会保障と税の一体改革」を進めています。
この改革に伴い、各省庁では社会保険の未加入事業所に対する対応が一層厳しくなっています。
例えば、建設業や運送業では、社会保険が未加入であることで、新規許可や免許の更新が出来ない他、仕事の受注が出来ない、車両の使用停止など、様々なペナルティーや影響が出てきています。また、その他の業種に於いてもハローワークに求人募集の掲載が出来なく人材確保に苦慮しているなど、今後更に、会社にとって様々なリスクが増えてくると予想されます。
会社にとってのリスクはそれだけではありません。後で述べる年金事務所による強制調査(強制適用)となれば、社会保険の加入が最大2年間さかのぼり、それと同時に保険料も発生しますので、何百万円・何千万円も納付しなければならない事態になります。
年金事務所は、どのように未加入事業所を把握しているのか。
現在、日本年金機構では、健康保険・厚生年金保険の保険料負担を避けるため、不正に加入していない会社が、全国で数十万事業所に上る可能性があると考えています。
このことから、新たに登記した法人は法務省の登記簿を活用しています。(国税庁でも同じことを行っています)また、古くからある法人については、事業を監督する監督官庁と連携し、情報交換を行いながら未加入事業所を把握しています。
さらに、その他の関係官庁からの情報であったり、従業員やその家族・関係者などからの内部情報、その他外部からの情報など、あらゆるところから情報が入り未加入事業所の把握をしています。
社会保険未加入事業所への対応と今後の動向
新規法人で社会保険未加入事業所に対しては、日本年金機構に委託されている民間会社から文書が届きます。これを放置したりした場合、その後年金事務所が直接動きます。また、先に述べた各官庁からの情報やその他の情報提供については、最初から年金事務所が取り扱います。
まず、年金事務所は社会保険未加入事業所(適用対象事業所)に対して、最初に「厚生年金保険・健康保険の加入について」という文書を送ります。内容としては「社会保険制度の重要性」「法人事業所は加入が義務付けされています」などという文章とパンフレット類が同封されており、「すみやかに加入手続きを行ってください。」と書かれています。
”その手紙は突然届きます”
「会社を創業して何年も経つのに、こんな手紙は初めて来た!」と、思われた社長さん。
実は、年金事務所では、あなたの会社が未加入であることをずっと前から把握していました。ただ、年金問題で人手が足りなく手が付けられない状況で、先延ばしにしていただけなのです!
いよいよ年金事務所が動き出したということです。
年金事務所では送った文書に期間を定め、会社から何のアクションもなければ電話を掛けてきたり、職員が会社を訪問したりします。その際、年金事務所ではおおよその労働者数は把握していますが、労働者(正社員・契約社員・パート・アルバイトなど)の人数や勤務時間、月の勤務日数などを聞いてきます。
これらの質問に色々な理由を付けてその場はしのげても、年金事務所が納得できる回答や情報(帳簿類)などをある程度提示しなければ、その後何度も電話や訪問などで接触を図ってきます。また、会社の不十分な対応などが長期間続くと、年金事務所は強制調査(強制適用)を行うこともあります。
そのため、いくら会社の経営状況等が悪く、加入できない状況であっても真摯な態度で質問に応じた方が賢明だと考えます。(会社の事情により、少しは相談に乗ってくれる場合もあります。)
★今後の未加入事業所の把握に関しては、平成26年度中に日本年金機構が持っている全国の約170万事業所のデータと国税庁のデータを照合して、更に未加入事業所を割り出すなど、国税庁との連携も強化されます。
また、このデータを基に、平成27年度から社会保険未加入事業所に対する加入促進を本格化し、調査等に応じない事業は法律に基づく立ち入り調査(強制調査)を行うとしています。
★平成28年10月には、短時間労働者(パートタイマー・アルバイトなど)への社会保険の加入拡大が、以下の条件で実施され、約25万人が加入すると見込んでいます。(当分の間は大企業のみに適用されます。)
このことから中小企業は、いずれ中小企業にも適用されるこの短時間労働者の社会保険適用拡大を見据えて、会社経営を考えなければならなくなります。
★短時間労働者の適用拡大(全ての条件を満たした場合、加入しなければなりません。)
- 週20時間以上の勤務
- 月額賃金8.8万円以上
- 勤務期間1年以上
- 学生は適用除外
- 従業員501人以上の企業
当事務所のサービス

内山社会保険労務士事務所では、早く正確な手続きはもとより、
制度に対する説明やアドバイスを行い
「お客様本位」の手続き代行サービスをご提供します。